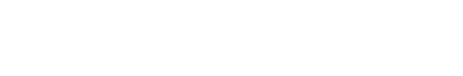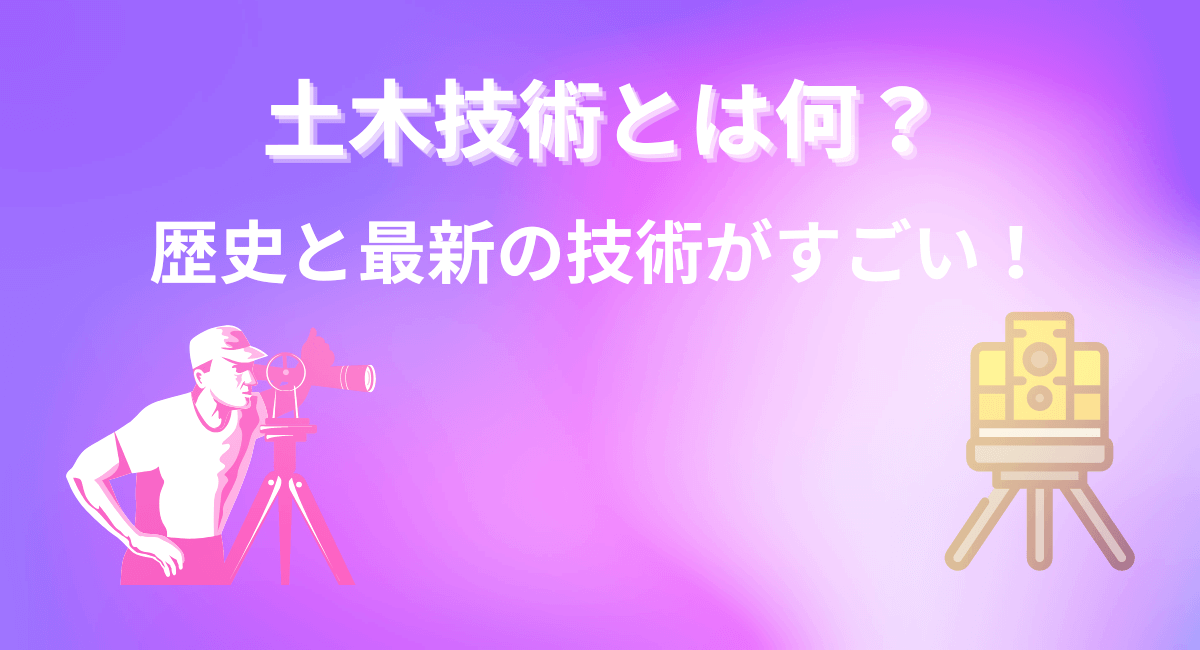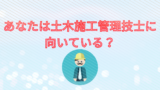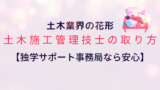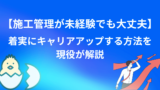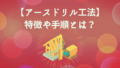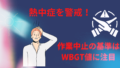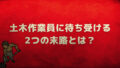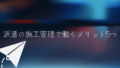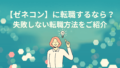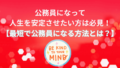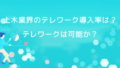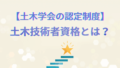「土木技術とは具体的にどんなことなのか?」と気になっていませんか?
結論を言うと、僕たち人間が生活するために必要な構造物や施設の施工計画・設計・施工・管理・改修・維持のすべてが土木技術の対象になります。
つまり土木技術は、人間が生活をする上で欠かせない事業です。
そこで本記事では土木技術について解説と併せて、歴史や最新の土木技術もいっしょに紹介していきます。
本記事を読むことで、土木技術のすべてが理解できるでしょう。
ちなみに土木工事の現場で技術が活かせるのは、土木技術者という職業の方のおかげです。
その土木技術者の仕事や必要なこと、そして最短で土木技術者になる方法もお伝えします。
あなたのやる気と行動次第では、2週間後には土木技術者としてデビューできます。

現役の土木技術者で、経験が9年の僕が解説するので、ぜひ参考にしてください!
なお下記の記事では、未経験から土木業界に飛び込む方法のすべてを解説しています。
これから土木技術者を目指す方にとって、非常に有益な情報なので併せてご覧ください。
土木技術とは?
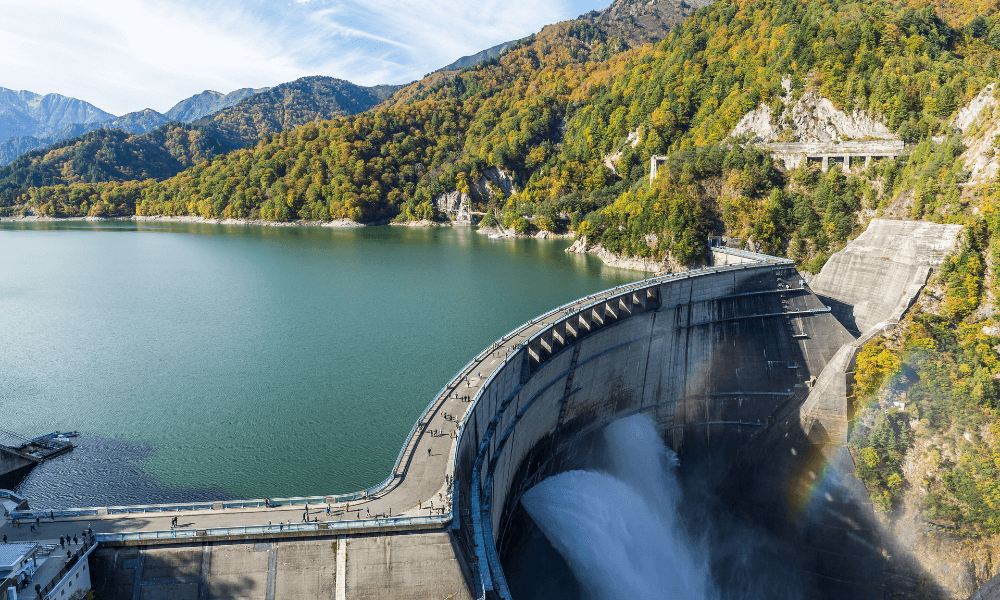
冒頭でもお伝えしましたが、人間が生活するために必要な構造物や施設の施工計画・設計・施工・管理・改修・維持を行うのが土木技術です。
さらに言えば、人々が安全・快適に生活できる環境を整備していくとも言えます。
意外にも生活に欠かせない土木の構造物や施設は、僕たちの身近に存在します。
たとえば、
- 道路
- 水路
- トンネル
- ダム
- 鉄道
- 橋梁
- 水道
- 河川
- 海岸
これらは僕たちの身近に存在していますが、土木技術を活かして作られた構造物や施設です。
また建物を建てるための土地が造成されたり、災害から身の安全が守られるのも土木技術のおかげです。

このように外に1歩出るだけでも、土木の構造物や施設を見る機会はあります!
普段はあまり意識しないので気付かないかもしれませんが、身近なところで土木技術が活躍しているのです。
会社は教えてくれない【土木技術の歴史】

土木技術の歴史は、人類の誕生と共に始まりました。
人間が生きていく以上は、住む場所や飲料水の確保はもちろん、歩くための通路も必要ですよね。
さらに安全を守る必要もありますし、食料もないと生きていけないため、そこから農業や集落がスタートしました。
つまり人間の生活を支えるのが土木なので、人類が誕生してすぐに歴史がスタートしたのは当然ですね。
しかし昔は穴を掘る重機や荷物を吊り上げるクレーンもなかったため、ほぼすべて人力作業だったでしょう。

だからこそ身体にかかる負担が、今とは比べ物にならなかったと思います!
加えて、今のように安全な構造物や施設を作ることも不可能だったはずです。
このように、土木技術には長い歴史があります。
そんな中で、土木技術を語る上で欠かせない人物が2人いることをご存知でしょうか?
その人物は以下の2人です。
- 古市公威
- 徳川家康
では1人ずつ紹介していきます。
古市公威
古市公威(ふるいちこうい)は江戸時代に生まれ、32才という若さで帝国大学工科大学(現在の東京大学工学部)の初代学長になった人物です。
さらに土木学会の初代学長でもあり、日本初の工学博士にもなっています。
古市公威が作った「豊平川水害防御計画図面」は、国の重要文化財にも指定されるほどです。
ちなみに、この図面は日本最古級の河川改修平面図になります。
札幌市を流れる豊平川は、明治時代に何度も氾濫を起こしていました。
この氾濫を防ぐために作られたのが、「豊平川水害防御計画図面」です。

古市公威は、この図面を基に2キロに渡る堤防と護岸、そして水門を完成させました!
でも当時の技術では豊平川の水圧には勝てなかったため、残念ながら1889年に決壊してしまいました。
しかし古市公威が作った福井市にある三国港突堤は、今でも九頭竜川河口を守っています。
徳川家康
徳川家康を知らない方は、ほとんどいないのではないでしょうか?
しかし、あくまでも学校で習う歴史上の人物としてしか知らないと思います。
実は土木の歴史でも、徳川家康は重要な人物なのです。
特に日本の首都であり最大級の都市でもある東京の土木の歴史を語る上では、徳川家康を忘れてはいけません。
なぜならド田舎だった東京(当時は江戸)に、
- 大規模なインフラ整備
- 運河と埋め立て地を作る
- 都市計画
上記の計画と実行を行い、大都会に生まれ変わらせたのが徳川家康だからです。
徳川家康は、豊臣秀吉の命令で当時はド田舎の東京に引っ越しました。
住むことになったのは江戸城、つまり今の皇居です。
普通の武将なら自身の力を見せつけるために、住居の改修を豪華に行うでしょう。
しかし徳川家康は江戸城の改修工事は最小限にし、インフラ整備や都市開発に力を入れました。
つまり土木工事の予算を自分のためではなく、住民のために使ったということです。
住民のために予算を使ったおかげで、田舎の荒れた土地だった東京は人々が住みやすい今の大都会へと変わったのです。
このように江戸時代でも令和でも、土木の根本的な目的は変わっていません。
それは「世界の人々が住みやすい構造物や施設を作ること」です。
今の土木技術があるのは、古市公威と徳川家康のおかげと言っても過言じゃありません。

ということで、土木技術の歴史で重要な人物2人の紹介でした!
進化し続ける最新の土木技術
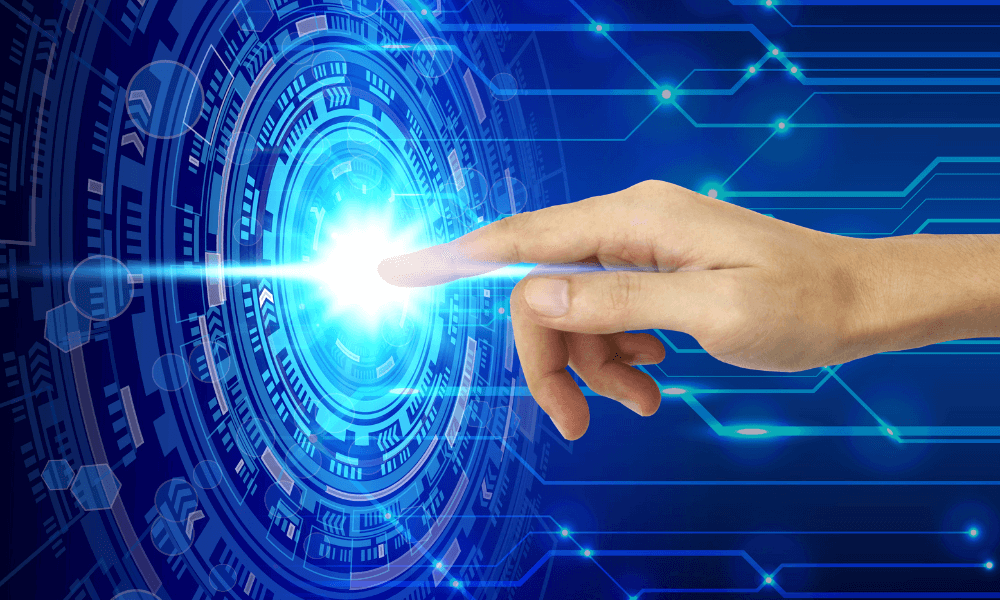
100年以上まえから土木の目的は変わっていませんが、技術はどんどん発展しています。
昔は現場の測量から設計・施工まで、そして図面を書くのも、基本的にすべて手作業だったと思います。
でも今はICTやAIの発達で、手作業は最低限です。
たとえば、土木工事は測量から始まります。
なぜなら現場の現況を図面にする必要があり、それを基に設計から施工まで行っていくからです。
この測量にしても、今は器械をセットすればボタン操作1つで、現場の現況を器械がデータとして暗記してくれます。
そのデータをパソコンに挿入し、あとは専用のソフトを使えば、現況の図面も出来上がります。
しかも測量器械は自動で座標も計算してくれるので、その座標を参考に完成図を作ることも可能です。
こんな感じで土木技術はどんどん発展しており、めんどくさい手作業が今は最小限になっています。
もちろん器械で測量したデータが基になっているため、正確性もバツグンです。

このように最新の土木技術は素晴らしいですし、これからの発展も楽しみですね!
土木技術者の役割は現場監督

土木技術者は、工事現場の監督として作業員たちに指示を出すのが役割です。
現場の測量や設計、施工計画、管理を土木技術者が行い、実際の現場の施工は作業員に任せます。
つまり現場では、作業員たちに安全で迅速に仕事をさせることが土木技術者の大きな役割になります。
土木技術者は現場で肉体労働はしませんが、工事の全責任を背負うためプレッシャーがかかる仕事です。

現場で発生した問題は、すべて土木技術者の責任になります!
このように土木技術者は作業員ではなく、あくまでも使う側として現場監督が役割です。
プレッシャーがかかる分、高給がいただけるので年収1,000万も目指せますよ。
土木技術者に必要なこと5つ

土木技術者に必要なことは、以下の5つです。
- チームをまとめる力
- 交渉する力
- 計画を立て仕事を進められる力
- 物事を冷静に判断する力
- 研究する力
現場監督として作業員たちに指示を出す立場なので、土木技術者は誰でもできる仕事ではありません。

だからこそ、それなりに必要なことがあります!
では1つずつ解説します。
チームをまとめる力
土木技術者に必要なことの1つ目は、チームをまとめる力です。
土木工事は、土木技術者が1人で行うわけではなく、作業員や重機オペレーターなど数人以上のチームで進めていきます。
そのチームをまとめていくのが、土木技術者です。
つまりチームのキャプテンのように自分のことだけではなく、チーム全体をまとめる力は必須です。

なので学生時代の部活でキャプテンをやっていたり、普段からリーダーシップがある方は向いているでしょう!
交渉する力
必要なことの2つ目は、交渉する力です。
土木技術者は、いろんな職人を使うので、計画した通りに作業をしてもらえるように交渉するのは日常茶飯事です。
また発注者に、「単価を上げてもらえないか?」交渉することもあります。

つまり、交渉する力を含めた最低限のコミュニケーション能力が必要ということです!
計画を立て仕事を進められる力
必要なことの3つ目は、計画を立て仕事を進められる力です。
そもそも、土木技術者は計画を立てるのが仕事です。
- この作業員には、この仕事を任せよう
- 来週には〇〇が必要だな
- 来月までに完成させられそう
上記のように、翌日だけでなく1週間、1ヶ月先の計画まで立てないと現場がストップしてしまいます。
作業員なら、その日に指示された仕事をすればOKですが、土木技術者がその日の思い付きで動くのはNGです。

なので、計画を立てて仕事を進められる力も土木技術者には必要でしょう!
物事を冷静に判断する力
必要なことの4つ目は、物事を冷静に判断する力です。
先述したように土木技術者には、計画を立てる力が必要になります。
ですが、すべてが計画通りに進むことはありません。
- 災害などで現場がストップする
- 現場で障害物が見つかる
- 発注者から急な変更を頼まれる
このように、現場では予定外のことが起きます。

そんなときでも、パニックを起こさず物事を冷静に判断する力が土木技術者には必要です!
研究する力
必要なことの4つ目は、研究する力です。
確かに先人たちによって、土木分野の技術や知識は解明されています。
でも現場によって施工方法も違いますし、土木技術の進化で、もっと効率の良い方法があるかもしれません。
それを見つけるには、研究あるのみです。
だからこそ土木技術者には、最新のやり方や自分に合った施工方法を見つけるために研究する力が必要です。
つまり、決まったことや言われたことしかやらない方には不向きな仕事と言えます。

以上が、土木技術者に最低限は必要なこと5つでした!
詳しくは、下記の土木施工管理技士に向いている人の特徴の記事も併せてご覧ください。
土木技術者は、「現場監督」や「土木施工管理技士」とさまざまな呼び方があります。
上記の記事は、土木技術者に向いている人を解説した記事なので参考になると思います。
土木技術者になる方法3つ

土木技術者は努力次第で誰でもなれます。
そこで、ここからは土木技術者になる方法を紹介しましょう。
土木技術者になるには、以下3つの方法が有利です。
- 大学・専門学校の土木学科を卒業する
- 土木技術者の見習いとして就職する
- 資格を取得する
では1つずつ解説します。
大学・専門学校の土木学科を卒業する
土木技術者になる1つ目の方法は、大学・専門学校の土木学科を卒業することです。
この方法では、学生をしながら土木技術者になるための専門分野を学ぶことができます。
土木系の学校の大半は、作業員ではなく土木技術者を輩出するためにあります。
なので大学・専門学校を卒業すると、新卒で土木技術者として就職できるということです。
また、後述する資格も最短で取得できるようになります。

ちなみに、僕も専門学校の土木科を卒業しています!
ですので、まだ10代などの若い方なら大学・専門学校で勉強しながら土木技術者を目指すのがおすすめです。
土木技術者の見習いとして就職する
2つ目の方法は、土木技術者の見習いとして就職することです。
大学・専門学校の土木学科を卒業した新卒でなくても、土木技術者の見習いとして就職できます。
シンプルに「未経験OK」の施工管理求人に応募すればOKです。

こちらは、新卒のように土木技術者として育ててもらえる待遇になります!
つまり働きながら資格の取得をし、土木技術者として1人立ちを目指していきます。
なので、もう20代後半で今さら学校に行く余裕がない方におすすめの方法です。
資格を取得する
3つ目の方法は、資格を取得することです。
土木技術者にどんな資格が必要か?は下記の記事を参考にしてください。
※「土木技術 資格」の内部リンク
実際、土木技術者に最も有利な資格は「土木施工管理技士」と「土木技術者」です。
これらの資格があれば土木技術者として就職もしやすいですし、人生も安泰になる。
でも正直「土木技術者」の資格はベテラン向けなので、まずは「土木施工管理技士」の取得をおすすめします。
ただし「土木施工管理技士」を取得できるまでは、実務経験が必要です。
なお必要な実務経験の年数は学歴で異なるので、下記の土木施工管理技士の取り方をご参照ください。
大学・専門学校の土木学科を卒業している場合、卒業後1~2年の実務経験で土木施工管理技士の受験資格が得られます。
いくら経験があっても、最終的には資格がないと土木技術者にはなれないので、がんばって取得しましょう。

ちなみに元々は作業員として土木業界に飛び込んだ方でも、経験を積み、資格を取得して土木技術者になる方もいます!
ですので、まずは作業員として気楽に働き、資格を取得してから土木技術者へキャリアアップするのもありだと思います。
土木技術者への近道とは?
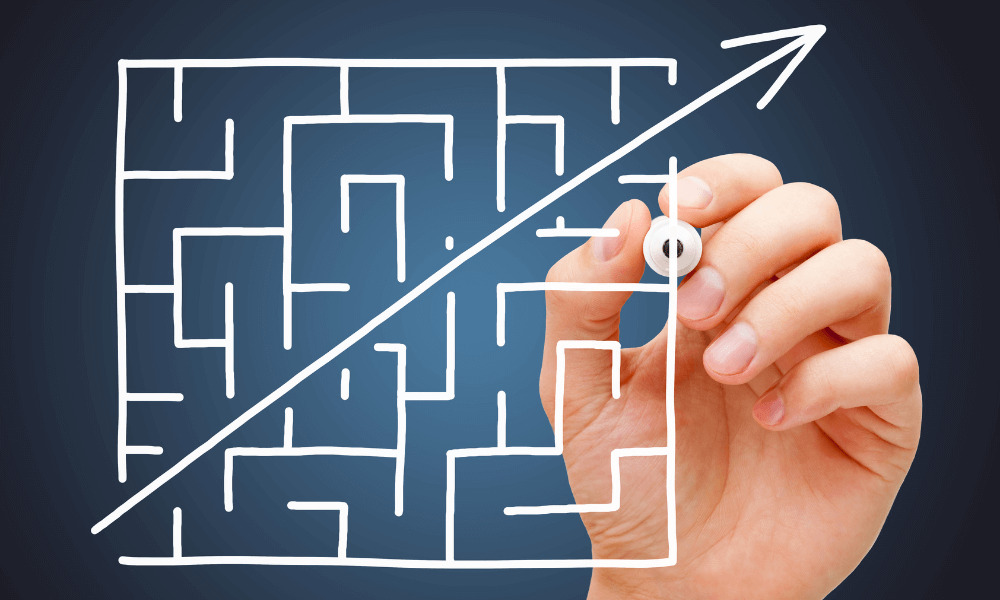
最初から土木技術者として業界に飛び込むことが、土木技術者への近道です。
つまり最短で土木技術者になりたいなら、作業員を経験せずに土木技術者の見習いとして就職するのがおすすめです。
実際、当ブログを読んでいただいている方は、30才前後の方が多いと思います。
つまり、今さら学校に通うヒマも余裕もないのではないでしょうか?
だとすれば、中途採用で土木技術者の見習いとして就職するしかありません。
確かに大学・専門学校を卒業すれば、土木施工管理技士を早く取得できるメリットがあります。
しかしメリットはそれだけなので、今から学校へ通うくらいなら就職して経験を積んだほうがいいでしょう。
そんな未経験の中途採用から、土木技術者を目指したい方におすすめなのがKSキャリアです。

KSキャリアは、建設・不動産業界の転職に強みがある転職サービスです!
そして建設のほうでは施工管理、つまりは土木技術者の転職を専門としています。
登録をすると業界を熟知したアドバイザーが、内定までに必要な活動をすべてサポートしてくれます。
完全無料なので、あなたが損する心配はありません。
「未経験OK」や「資格不問」の求人も多く保有しているため、未経験の方も安心です。
つまり土木技術者の先輩に仕事を教えてもらいながら、資格の取得が目指せるということです。
実際、建設業界が未経験のフリーターから、土木技術者への転職に成功した方もいます。
業界と職種に特化している分、内定までの期間も短く、最短2週間で転職先が決まるのが驚きです。
内定後の定着率も92%なので、今まで長く仕事が続かなかった方もKSキャリアで紹介される企業なら安心して働けるでしょう。
相談だけでもOKなので、転職するか決まっていない方でも、土木技術者に興味があるなら気軽に登録しておきましょう。
下記からKSキャリアの公式サイトへ飛べます。
ちなみに、登録は5分もあれば十分です。
KSキャリアの登録方法は、下記の記事で紹介しているのでご安心ください。
まとめ
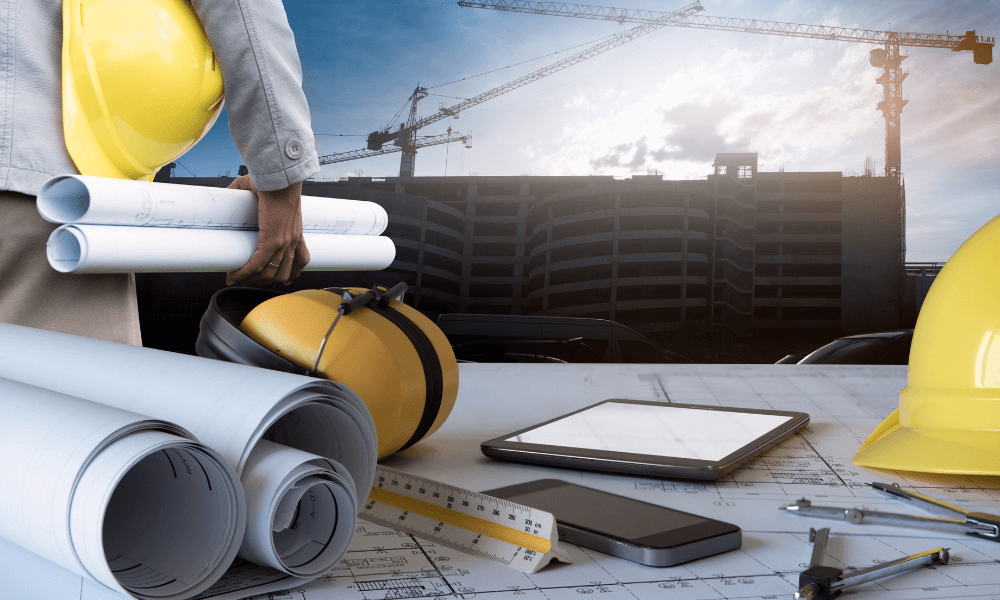
人間が生活するために必要な構造物や施設の施工計画・設計・施工・管理・改修・維持のすべてが、土木技術に該当します。
少しだけ意識を変えてみると、僕たちの身近で土木技術が大きな活躍をしています。
土木技術の歴史も長く、人類の誕生と共にスタートしました。
つまり、人間が存在する以上は土木の仕事も存在するので十分な将来性があるでしょう。
なので土木技術を極めると、食いっぱぐれる心配はありません。
土木技術はどんどん進化しており、これからが楽しみな業界だと思います。
そしてこの高い技術を活かした土木技術者の役割は、現場監督です。
つまり現場で泥まみれになって作業するのではなく、あくまで管理が仕事です。
測量や設計、施工計画などは土木技術者が行い、実際の施工は作業員たちに任せます。

土木技術者はプレッシャーがかかりますが、その分だけ給料も高めになります!
もし土木業界に興味があるなら、土木技術者を目指してみませんか?
学歴は関係ないですし、KSキャリアを経由すれば採用もされやすいでしょう。
なぜならKSキャリアは、多くの建設会社と取引がある転職サービスだからです。
これこそが、建設業界の転職に強みがある最大の理由です。
未経験OKの求人も多く所有しているため、誰でも土木技術者に挑戦するチャンスが与えられます。
また完全無料で、履歴書の添削や面接時のアドバイスなど手厚いサポートが受けれるため超お得です。
実際に転職するか決まっていなくても、相談ができるので、この機会にひとまず登録だけでもしておきましょう。
KSキャリアへの登録は、下記からどうぞ。