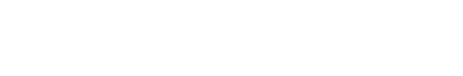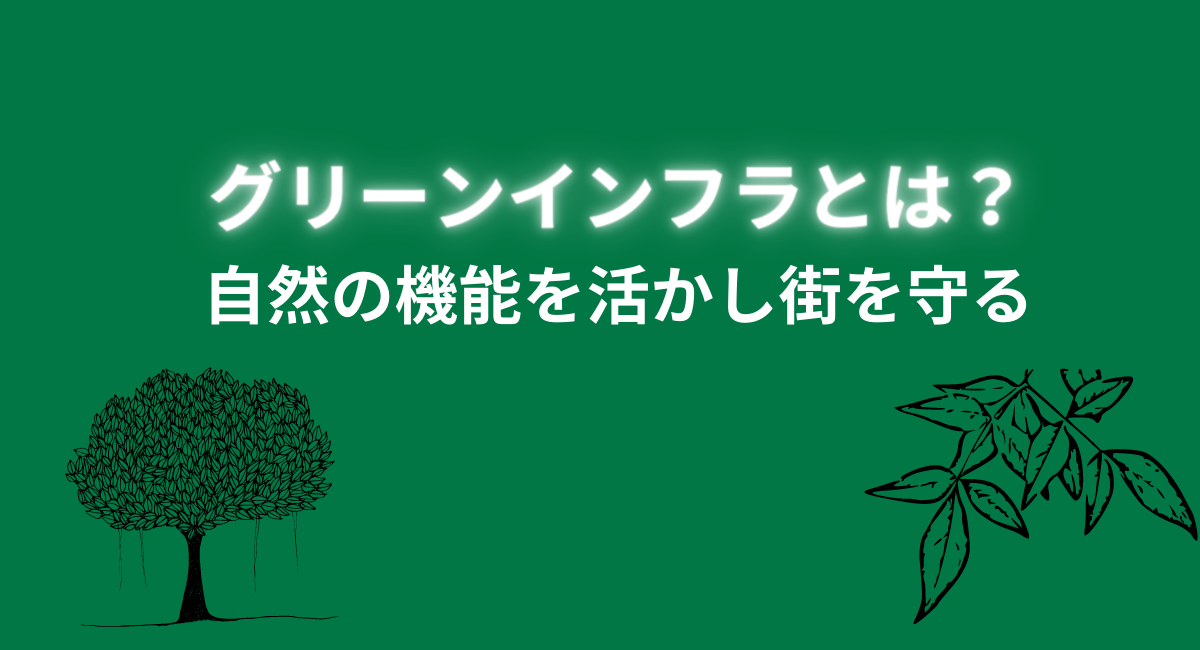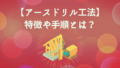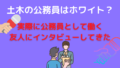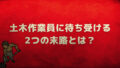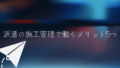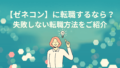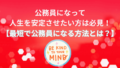「グリーンインフラとは何?」と気になっていませんか?
実際「聞いたことはあるけど、詳しくは分からない」という方も多いと思います。
グリーンインフラは、自然の機能や仕組みを利用し緑で溢れる街づくりをすることです。
でも緑を増やすだけでは、ダメなのも事実なのですね。
実は、国土交通省が考えるグリーンインフラには3つの要素があります。
その要素も踏まえて、本記事では建設業界で10年働く僕がグリーンインフラについて徹底的に解説していきます。
日本で実際に行われた事例も紹介するので、より具体的にイメージできるはずです。
本記事を読むことで、あなたも「グリーンインフラは〇〇です」と人に説明できるようになるでしょう。

今後の課題も解説しているので、街づくりに携わる仕事に興味がある方は、ぜひ参考にしてください!
グリーンインフラとは?分かりやすく解説

グリーンインフラとは、グリーンインフラストラクチャー(Green Infrastructure)の略です。
僕たちの生活に必須の社会資本であるインフラに、グリーン(緑)を付け加えたシンプルな単語になります。
ちなみにグリーン(緑)は、自然を意味します。
つまりグリーンインフラとは、自然が持つ機能や仕組みをインフラ事業に有効活用する考え方のことですね。
自然の機能や仕組みを有効活用することで、災害から身を守る設備ができます。
さらに「地球温暖化の対策」や「自然生物の保護」もでき、持続可能な社会の実現にも繋がります。
要するに、ただ緑豊かな街を作るのではなく、防災や地域の振興も考える必要があるということです。
「具体的にどんなことをするのか?」ですが、本記事では事例も紹介するので、そちらを参考にしてください。

今はグリーンインフラとは、「自然の力をインフラ事業に活用し国土を豊かにしていく考え方」と覚えておきましょう!
なぜグリーンインフラが必要なのか?
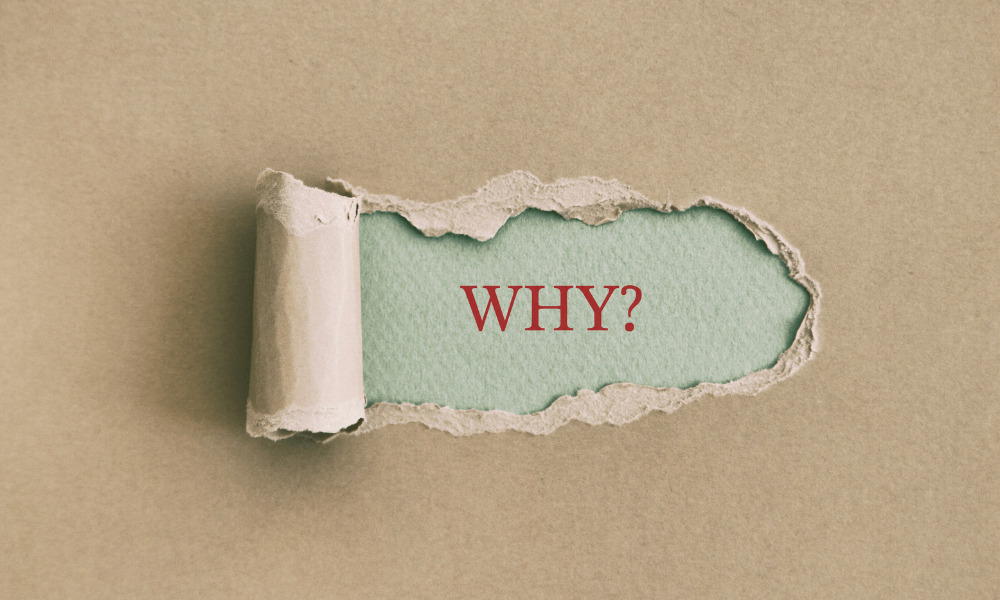
今は成熟社会であり、便利なプラットフォームや物で溢れる時代ですよね。
たとえばスマホ1台あれば暇つぶしや情報収集ができ、不自由のない暮らしができるのが日本の良いところです。
しかし便利な物やサービスと併せて、ネットワークや制度も充実した成熟社会だからこそ、自然の豊かさが求められてきました。
ちなみにグリーンインフラは、2007年にアメリカで誕生した言葉です。
既にアメリカも成熟社会を迎えており、自由な暮らしと併せて豊かな自然環境で人々が健康的に暮らせる社会の実現が求められました。
このように人間が創出した多様な便利な物やサービスにより、自然の良さが忘れられてきたのです。
だからこそグリーンインフラにより、もう1度人々と自然が深く関われる環境を作ることが、これから必要になってくるでしょう。
また自然災害による被害が近年では問題となっており、これを解決するには防災や減災するための早めの対応が課題です。
そこで自然が持つ機能や仕組みを上手く活用し持続可能な国土を作るためにも、グリーンインフラは欠かせません。

グリーンインフラの導入でSDGs(持続可能な開発目標)の達成も期待できるのです!
グリーンインフラの考え方【国土交通省が発表】

国土交通省はグリーンインフラの成立について、以下3つの要素があると考えています。
- 防災・減災
- 環境
- 地域振興
上記の3つが、持続可能な社会の実現や国土の適切な管理に繋がるということです。
それぞれ順番に解説します。
防災・減災
大雨や台風など、自然災害による被害は常に意識する必要がありますよね。
グリーンインフラは、この自然災害から街や人々を守ることが目的の1つです。
たとえば東京都では、雨水対策としてコンクリート管やプラスチックで地下調整池が建設されました。
地下50mに直径約12.5m、流さ4.5kmの巨大トンネルを作ったことで、雨水の54万㎥を一時保留し浸水被害を軽減する狙いです。
雨水を溜めておく設備がないと、下水道や河川に直接流れてしまい河川が氾濫する原因になります。
そこでニューヨーク市でも、グリーンインフラを活用し、こんな水害対策が行われました。
単純ですが、ずっとアスファルトがむき出しだった道路わきの側溝を緑化させただけです。
一見、何の変化もないように見えますが側溝を緑化することで、道路に降った雨水を流し込む手法になります。
つまり、「土の中に浸透させる」というシンプルな手法です。

このように自然の力を使い、防災・減災に繋げることがグリーンインフラが成立する要素の1つです!
環境
グリーンインフラは、「防災・減災だけできればいい」というわけではありません。
自然の機能を活かした街づくりも、考える必要があります。
たとえば大阪ではグリーンインフラを活かした街づくりとして、緑に包まれた歩道を建設しました。
大阪で行われたグリーンインフラを活かした街づくりは、大阪府の住宅まちづくり部さまの資料を参考にしてください。
人々の憩いの場になったことに加えて、建物の周辺に植えられた植物は水分を蒸発させる働きがあります。
つまり熱を逃がすため、緑に包まれた街づくりはヒートアイランド現象を防ぐことにも繋がります。
ヒートアイランド現象とは、主に都市部などコンクリートに覆われたエリアが高温になる現象のことです。
コンクリートやアスファルトは熱を溜め込む性質があり、郊外に比べて都市部では気温が約3度も上昇します。
ですので熱を奪う緑地や河川を増やすことが、ヒートアイランド現象を防ぐ対策になります。

あくまでも防災・減災だけでなく、環境の保全もすることでグリーンインフラが成り立つのです!
また森林や河川を始めとした自然環境を大きく変えることで、生態系を崩さないよう注意も必要です。
自然の環境を変えたために、住処を失う生物がいるかもしれません。
そもそも生態系は、それぞれが上手く噛み合うことで役割を果たすことができます。
どれか1つの生態系が役割を果たすことができなくなれば、環境を壊すことになり本末転倒です。
つまり人間が生活する環境だけでなく、生態系も生き延びられる環境を保全することがグリーンインフラで持続可能な社会を形成できます。
地域振興
「地域振興」の意識を持ってグリーンインフラに取り組み、緑や水を増やしていくと人々にレクリエーションの場を提供できます。
たとえば公園の建設が、グリーンインフラによる「地域振興」の代表格です。
子どもたちにとって公園は、これ以上ないレクリエーションの場でしょう。
その公園に芝生を張り緑を増やすことで、子どもたちのケガや熱中症対策にもなります。
先述したように植物には水分を蒸発させて、熱を逃がす働きがあります。
だからこそ、グリーンインフラによる公園の建設は大きな「地域振興」です。
公園は、学校の授業でも利用されることが多い場所だと思います。
ですのでグリーンインフラにより「地域振興」を考えることは、人々に憩いの場も提供できるのです。

以上がグリーンインフラが成立する3つの要素でした!
- 防災・減災
- 環境
- 地域振興
国土交通省が考えるグリーンインフラの要素なので、参考になると思います。
日本で実施したグリーンインフラの事例4つ

グリーンインフラが日本に導入され、行政から本格的に推進されるようになったのは平成25年頃です。
それから約10年が経つ今日まで、日本で実施されたグリーンインフラの事例を4つ紹介します。
- 気候変動への対応
- 投資や人材を呼び込む都市空間の形成
- 持続可能な国土利用・管理
- 低利用地の利活用と地方創生
前項のグリーンインフラが成立する3つの要素がすべて該当しているので、そこに注目してみましょう。
では順番に解説します。

ちなみに、こちらは国土交通省が提供する「グリーンインフラの事例」の資料を参考にさせていただきました!
この資料では、より具体的にグリーンインフラの事例が見れますよ。
気候変動への対応
最初に紹介するグリーンインフラの事例は、横浜市の取り組みです。
グリーンインフラにより、総合治水対策とヒートアイランド対策が同時に行われました。
その取り組みとは公共施設や公園など、さまざまな場所に「透水性舗装」や「浸透ます」の整備です。
また住宅や建築物の敷地へも「雨水浸透ます」や「雨水貯留タンク」を設置し、大雨などによる水害を防ぐための対応もしています。
雨水が地面に浸透し植栽に流れ込むので、植栽の成長も期待できます。
植栽(緑地)が成長するほど熱を逃がす仕組みができるため、同時にヒートアイランド現象への対策にもなるでしょう。

つまりグリーンインフラが成立する1つ目の要素である「防災・減災」に重点をおきつつ、「環境保全」もできているということです!
投資や人材を呼び込む都市空間の形成
2つ目に紹介するのは、東京の二子玉川で実施されたグリーンインフラの事例です。
民間再開発と都市公園の整備により、投資や人材を呼び込む都市空間を形成する狙いです。
緑で溢れる広場や遊歩道の整備は、地域振興に繋がります。
さらに水害対策もされた都市公園の整備もされたため、周辺の生態系の崩壊を防ぐことも可能です。

つまり二子玉川ライズと二子玉川公園の連携により、グリーンインフラが実施された事例になります!
持続可能な国土利用・管理
3つ目に紹介するのは、日本各地で実施されたグリーンインフラの事例です。
国土を無駄にせず、むしろ国民のためになるよう最適な利用・管理ができる取組の考案を求められました。
そこで、たとえば北海道の石狩市では国土の良好な状態を維持するため、車の乗り入れを規制する柵の補修が行われました。
加えて、利用マナーの向上を呼びかける活動も行っています。
他には愛知県の豊田市の山林で、不要な木を間伐したことで洪水被害の軽減が期待できます。

このように適切な国土の利用・管理が、持続可能な社会の実現に繋がるでしょう!
低利用地の利活用と地方創生
最後に紹介するのは、グリーンインフラにより低利用地の利活用と地方創生を行った事例です。
こちらは簡単に言うと、有効な土地利用ができていない地域をグリーンインフラで活性化させることです。
つまり「どうすれば人々が暮らしやすくなるか?」を考えるので、地方創生にも繋がります。
実際に低利用地だった土地を子どもたちの遊び場になる広場にしたり、ボランティア団体の憩い場にした事例があります。
特に地方では、人口の減少により空き家が目立つ地域が多いでしょう。
そのような地域を、有効に活用することやレクリエーションの場にすることがグリーンインフラです。
ここまでが日本で実際に行われたグリーンインフラの事例4つでした。

詳細は国土交通省が作成した参考資料の「グリーンインフラの事例」をご覧ください!
グリーンインフラのデメリットと今後の課題4つ

防災できたり、きれいな街づくりができるため、グリーンインフラの導入自体にデメリットはないと思います。
しかし施工する企業や管理する行政の視点から見て、デメリットと今後の課題はあります。
グリーンインフラのデメリットと課題は以下の4つです。
- 時間と手間がかかる
- 整備費用が莫大
- 公共事業では普及しにくい
- 住民の同意を得にくい
では順番に解説します。
時間と手間がかかる
グリーンインフラのデメリットとして、「時間と手間がかかること」が挙げられます。
ここまで解説してきたようにグリーンインフラは、緑化に伴うことが多くなります。
つまり草や木を植えるわけですが、1日や2日で育つものではありません。
だからこそ、土木工事よりも圧倒的に時間がかかります。
さらに植物を育てるので、当然「水やり」などのメンテナンスも必要です。

このように施工するだけでも時間がかかりますし、そのあとの整備にも大きな手間がかかるのはデメリットでしょう!
整備費用が莫大
デメリットの2つ目として、「整備費用が莫大なこと」も挙げられます。
実際、グリーンインフラの施工はコンクリート工事やアスファルト工事に比べて整備費用が高くなります。
そのため発注者からすれば、予算について慎重に考える必要があるでしょう。
ちなみに、もし金銭的に厳しい場合はグレーインフラを実施する手もあります。
グレーインフラとは、コンクリート構造物であり従来型の社会の基盤です。
ですが、グレーインフラは以下がデメリットです。
- 災害による被害が拡大する
- 復興に時間と費用がかかる
- 生態系が崩壊する

上記のデメリットがあるからこそ、グリーンインフラが推進される時代になりました!
公共事業では普及しにくい
ここからは、グリーンインフラの今後の課題を紹介します。
そんな課題の1つ目は、公共事業ではグリーンインフラが普及しにくいことです。
公共事業で普及しにくい理由は、今の時点ではグリーンインフラの技術指針が確立されていないためです。
また、グリーンインフラによる効果の証明も明確ではありません。
そのため「マニュアル通りに施工」が求められる公共事業では、手が出しにくいのでしょう。

だからこそ明確な指針を確立させていき、グリーンインフラを官民連携で進めることが今後の課題と言えます!
住民の同意を得にくい
2つ目の課題は、「住民の同意を得にくいこと」が挙げられます。
実際にアメリカの行政職員の約40%が、「住民との関わり方が課題」とアンケートで回答しています。
つまり、住民の同意を得た上でのグリーンインフラの実施が難しいということです。
確かに街の環境が変わってしまうことに、不満を持つ方もいるでしょう。
住民の憩いの場を作ることもグリーンインフラの目的ですが、「需要があるか?」を事前にリサーチすることは難しいと思います。

そのため住民に同意をしていただき、緑で溢れる街づくりを気持ちよく施工できるような取組が今後の課題です!
グリーンインフラに強い企業3社

ここからは、グリーンインフラを得意とする企業3社を紹介します。
以下3つの企業は、グリーンインフラに関連する技術がトップクラスです。
- 鹿島建設さま
- 東邦レオ株式会社さま
- 物林株式会社さま
では1社ずつ解説します。
鹿島建設さま
鹿島建設さまは、日本トップクラスのスーパーゼネコンです。
そして、建設業界でもトップクラスの高い技術があります。
この鹿島建設さまは、もちろんグリーンインフラも提供するサービスの1つです。
実際にテナントスペースに空きが多く、売上も減少していた商業複合ビルをグリーンインフラにより、
- 不動産価値の向上
- 話題になり入居率も向上
- ゴミの処理費の削減
長年培ってきたグリーンインフラの技術と知識を活かし、不動産価値と集客力の向上に貢献した実績があります。
つまり鹿島建設さまは、この業界の代表と言える企業です。

その他のグリーンインフラによる鹿島建設さまの実績はホームページからご覧になれます!
東邦レオ株式会社さま
東邦レオ株式会社さまは、グリーンインフラを主体とする企業です。
1965年に創業し、今では全国に支店があります。
この東邦レオ株式会社さまはグリーンインフラの専門企業として、主に関東の緑化をしてきました。
また施工だけでなく、グリーンインフラによる街づくりのサポートも行っています。
セミナーや勉強会も開くほどなので、グリーンインフラのプロ中のプロと言えるでしょう。

ですのでグリーンインフラに興味がある方は、東邦レオ株式会社さまの公式サイトを1度チェックしてみるといいかもしれません!
物林株式会社さま
物林株式会社さまも、グリーンインフラを事業としています。
整備から企画・設計・施工・管理までグリーンインフラのすべてを展開するのが、物林株式会社さまの特徴です。
実際、グラウンドや公園など多くの施設を緑に包んできた実績があります。
また国内の有力メーカーから緑化資材を仕入れており、建設会社や造園会社に提供も可能です。
つまり緑化事業なら、物林株式会社さまに相談すれば間違いはないでしょう。

詳細は、物林株式会社さまの公式サイトをご覧ください。
グリーンインフラに携わるには建設コンサルタントがおすすめ

本記事をここまで読んでくださった方には、「グリーンインフラに携わる仕事がしたい」という方が多いのではないでしょうか?
実際グリーンインフラは、いま学生からも人気を集めている分野でもあります。
そこで今からグリーンインフラに関係する仕事を始めるなら、建設コンサルタントへの転職がおすすめです。
建設コンサルタントは、インフラ整備の事前調査を行い、設計・計画をクライアントに提案する仕事です。
つまり、「どのような施工をするか?」を常に研究しながらコンサルティングします。
もちろん街づくりに関係する工事も多いので、グリーンインフラに深く関わる可能性が最も高い職種でしょう。
実際に「グリーンインフラ 転職」と検索をかけると、建設コンサルタントの求人が多く出てきます。
たとえば大手転職サービスのdodaでは、本記事でも紹介した鹿島建設さまの求人も掲載されています。
dodaは業界トップクラスの求人数があり、完全無料でプロの充実した転職サポートを受けることが可能です。
「経験不問」や「第二新卒歓迎」の建設コンサルタント求人もあるので、1度dodaで相談してみてはいかがでしょうか?

利用も相談も完全無料ですし、未経験の業界への転職はプロの支援があれば安心だと思います!
約20万件の求人を保有し、求職者1人ひとりに合った仕事を紹介してくれるdodaへの登録は下記からどうぞ。
まとめ
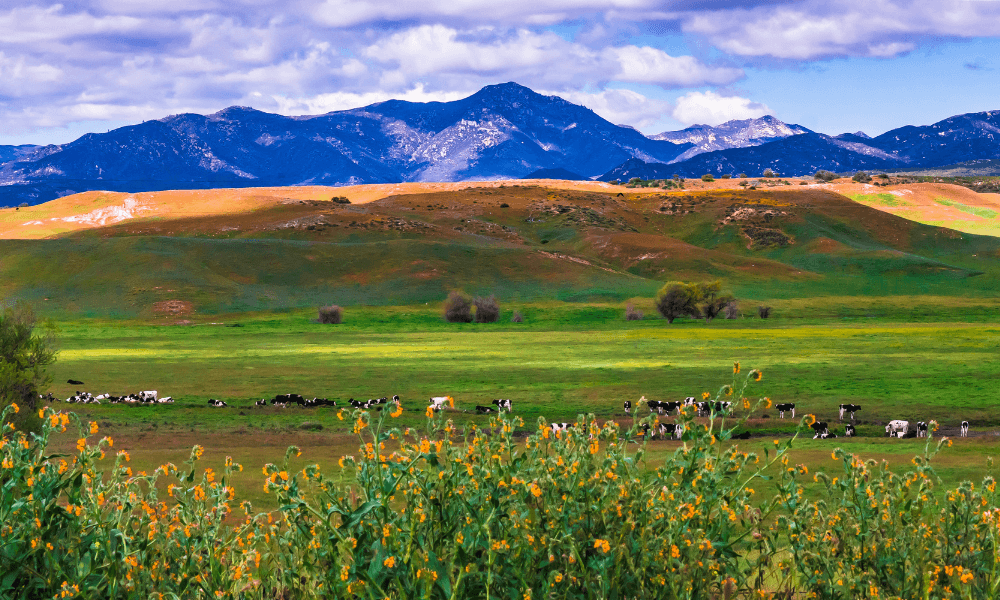
グリーンインフラストラクチャー(Green Infrastructure)は、自然の機能や仕組みを活かして国土を豊かにすることを目的としています。
具体的には緑で溢れる街づくりと同時に、以下の3つを目指していくことです。
- 防災・減災
- 環境の保全
- 地域振興
この3つの要素があってこそ、グリーンインフラが成立します。
自然が持つ力は無限であり、防災ができたり、住民の憩いの場を作ることができます。
本記事では事例も交えて、グリーンインフラについて徹底的に解説してきました。
グリーンインフラは平成25年頃に日本に導入されて以降、どんどん浸透してきています。
それまではグレーインフラが主流でしたが、これからはグリーンインフラの時代になっていくでしょう。
グリーンインフラは、素敵で安全な街づくりに携わる魅力的な仕事だと思います。

でも今は、建設業界が全体的に人手不足です!
なので未経験でも20~30代と若かったり、やる気のある方を求めている企業は必ずあるはずです。
まずは、転職のプロに気軽な無料相談から始めてみませんか?
下記の記事では、おすすめの転職サービスをニーズ別で紹介しています。
加えて未経験の方でも、建設業界に転職できる理由を業界歴10年の僕が解説しているので引き続き参考になれば幸いです。